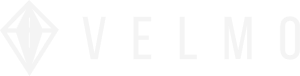特定小型原付は軽車両に分類される?法律とルールを解説

特定小型原付は、電動で手軽に移動できる乗り物ですが、軽車両に分類されるのかどうかについては疑問を持つ人も多いでしょう。
本記事では、特定小型原付の法的な分類や交通ルール、軽車両との違いについて詳しく解説します。
特定小型原付は軽車両に分類されるのか?
1. 軽車両の定義
道路交通法における軽車両とは、自転車やリヤカー、馬車などの非動力車両を指します。
|
車両区分 |
主な例 |
|
軽車両 |
自転車、リヤカー、馬車 |
|
原動機付自転車(原付) |
50cc以下のバイク |
|
特定小型原付 |
電動キックボード、電動モビリティ |
2. 特定小型原付の法的分類
特定小型原付は、軽車両ではなく「原動機付自転車」の一種として扱われます。
つまり、軽車両のルールではなく、原動機付自転車としての規則に従う必要があります。
軽車両と特定小型原付の違い
1. 免許の必要性
|
車両区分 |
免許の要否 |
|
軽車両 |
不要 |
|
特定小型原付 |
一部免許不要(条件あり) |
特定小型原付は、最高速度20km/h以下の場合は免許不要ですが、それ以上の速度が出るモデルは運転免許が必要です。
2. 走行可能な道路
|
車両区分 |
走行場所 |
|
軽車両 |
車道、専用自転車道 |
|
特定小型原付 |
車道、特定の歩道(低速モード時) |
特定小型原付は、一定条件のもとで歩道の走行が認められる場合がありますが、軽車両(自転車など)は基本的に歩道走行は禁止されています。
特定小型原付を安全に利用するために
1. 交通ルールを遵守する
-
歩道走行は制限あり(低速モードのみ許可)
-
車道では車と同じ交通ルールが適用される
-
信号や一時停止のルールを守る
2. ヘルメットの着用(推奨)
特定小型原付ではヘルメットの着用が義務ではない場合もありますが、安全のために推奨されます。
3. 違反時の罰則
交通違反をすると、反則金や罰則の対象になる可能性があるため、十分注意が必要です。
まとめ
特定小型原付は、軽車両ではなく「原動機付自転車」の一種として分類され、異なる交通ルールが適用されます。
-
軽車両(自転車)とは異なり、原動機を搭載しているため別のルールが適用
-
車道走行が基本であり、一部条件下で歩道走行も可能
-
適切なルールを守って、安全な利用を心がけることが重要
正しい知識を持ち、安全運転を心がけましょう。